
| (1) | 地域事業者の支援ニーズの高度化・多様化のなか、商工会・商工会議所が実施してきた経営改善普及事業は、事業創設から42年が経過し、その実施方法や実施体制が問われつつあり、本県においても、その見直しが緊急な課題。 |
| (2) | 中小企業基本法改正後、国の小規模企業政策の見直しのなかで、「大半の商工会が小規模で事業者支援を行う体制がぜい弱であるため、①多様なニーズに少人数の経営指導員で対応することが困難、②経営指導員等が研修等により資質向上することが困難・・・との問題が指摘されるなど、商工会・商工会議所の広域化・合併により、組織を拡大し事業実施体制を強化していく必要性が高まっている。 |
| (1) | 力を入れたい経営方策は、①新市場の開拓(54.6%)、②新商品開発(46.5%)、③人材育成(40.6%)→(開発力と販売力が経営革新の両論、それを担う人材育成がポイント) |
| (2) | 事業拡大や創業、情報化等新たな課題について、相談先不明とする企業が多く、地域の事業者の重要な相談先である商工会・商工会議所の対応力強化が望まれる。 |
| (3) | 現状の地域密着型の身近な相談指導を評価する企業も存在、身近な相談機能は維持しつつ、きめ細やかな支援を継続することも重要。 |
| (4) | 市町村が商工会等に望む機能は、経営相談の強化が最も多いが、街づくりやむらおこしなど幅広い分野で機能強化を要望。 |
☆組織の小規模性からくる人事上の閉塞感、長期研修受講の困難性(経営指導員等の専門性が不足)
☆情報化対応や新分野進出等新たな課題分野での満足度が低い
☆街づくりなど幅広い役割を期待されているが、担当職員の専門性の不足や財政的な基盤の弱さから、その対応力に限界
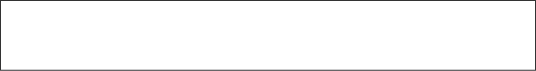
商工会等職員
の資質の向上
☆現行経営指導員による指導は、会員個々の事業ニーズの分析やその潜在的課題の整理、解決力が不足。
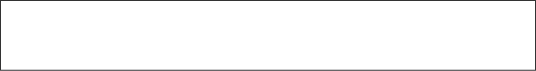
☆会員の経営環境の悪化、高齢化等は会員減少と会費収入の低迷を招き、安定した経営支援活動の基盤を浸食
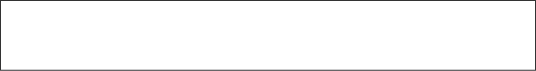
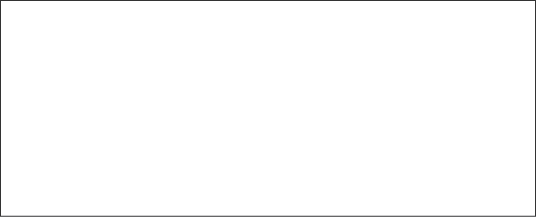
(1)役職員の意識の改革
(2)組織体制の見直し
(3)商工会等職員の資質の向上
(4)支援業務の高度化と効率化
(5)自律経営基盤の強化
(6)各種団体との連携の強化
(7)市町村との連携の強化

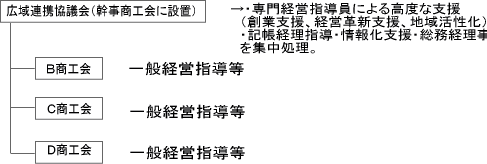
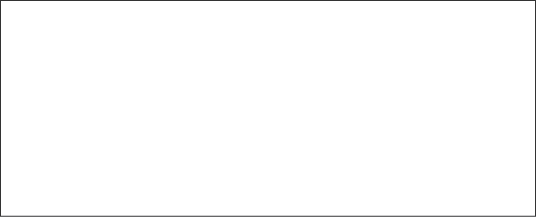
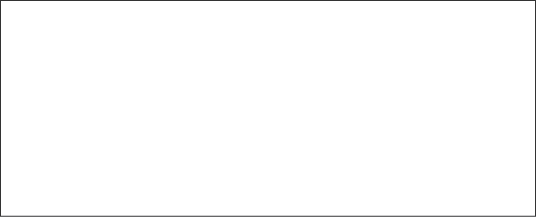
| 【商工会等職員の資質向上】 経営指導員のより一層の資質の向上を図るとともに、従来補助的な業務等に従事してきた補助員・記帳専任職員についても、情報化対応業務や基礎的な経営相談・指導業務など多角的な分野までその職務を拡充 |
|
【支援業務の高度化と効率化】 |
|
【自立的経営基盤の強化】 |
|
(1)「マスタープラン実施本部」の設置 |
本プランに示した各種改革項目については、早急に実現化することが重要。こうしたことから、本プラン策定後、直ちに県商工会連合会に「マスタープラン実施本部」を設置し、その実現化に向けた課題整理や実施プログラムの検討を行い、本プランの早期実現化に努める。 |
①モデル地域の選定と業務広域化の試行・段階的実施 |
県全域で、一律に広域体制に移行することは無理があることから、平成14年度内にも1ヶ所程度モデル地域を選定し、同地域内で業務の広域化等を試行するなどそのメリット・デメリットを検証しつつ、現行体制から広域体制への円滑な移行を図る。 |
②商工会改革集中期間の設定 |
当面3年を「商工会改革集中期間Ⅰ期」また、その後2年を「商工会改革集中期間Ⅱ期」と定め、集中的に改革を実施し、Ⅱ期期間終了までに県全域で広域体制への移行を完了。 |
|
(2)プラン策定後の継続的な検証 |
「商工会・商工会議所の広域的実施体制に係るマスタープラン策定委員会」については「仮(仮称)商工会・商工会議所の広域的実施体制に係るマスタープラン検証委員会」に組織替え。 |
| ☆ | 地域事業者の自主的な経済団体として自律した経営基盤を確立し、地域に根ざした各種事業を積極的に展開する商工会・商工会議所 |
| ☆ | 地域に身近な相談窓口と高度な支援能力を有する専門スタッフを併せ持ち、 “成長する企業づくり”を積極的に行う商工会・商工会議所 |
| ☆ | 地域の行政や各種団体、住民の結節点・地域プランナーとして、”魅力あるまちづくり”のため、積極的に行動する商工会・商工会議所 |